  since2022 |
サイクルショップシルクロード 奈良県生駒市真弓2丁目4-10 ℡0743-79-9592 (定休) 水曜日 |
||
 |
 |
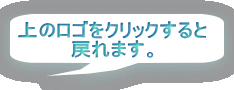  |
||
| 熊野本宮大社で祀られている八咫烏 | |||
サイクルショップシルクロードのシンボルマークであり、今回の新しい自転車ブランドとして名付けられたヤタガラス。一体それはなんなのでしょうか。 ヤタガラスは漢字で「八咫烏」と書きます。烏(からす)というだけあって鳥(とり)のカラスです。八咫というのは大まかにいうと大きいということで、大きなカラスという意味になります。 特徴としては、体が普通のカラスに比べて非常に大きい、ということと、なんと足が3本もあるということです。3本ある足のそれぞれが天、地、人を表しているそうです。 では、そんなカラスが存在していたのでしょうか。 それは古事記、日本書紀に出てくる時代。要は日本の神話の時代にさかのぼります。  【↑:神武天皇が奈良へ行進した時の経路】 ※詳しい経路はわかりません。想像です。 はるか昔、日本の初代天皇である神武天皇という人が、西の方から近畿地方、今の奈良盆地を治めるために兵隊を連れて進行してきました。 今でいう大阪側から生駒山を越えて奈良盆地に来ましたが、そこの地の民と戦争になり敗れてしまいます。 そこで一度また大阪湾まで撤退し、船で紀伊半島をぐるりと回り、和歌山県熊野まで行き、紀伊半島の山岳地帯を縦走し、また奈良へ攻め入ろうとしました。 今でいう熊野あたりで上陸し、紀伊半島の内陸の山岳地帯を目指すことになります。 しかし、当時の紀伊半島は当然国道169号線も、伯母峰トンネルも、ましてや道の駅もありません。地元の人間ですら越えることが難しい山岳地帯を、よそから来た神武天皇一軍が越えられるわけがありません。 そこでまたなんやかんやあったわけですが、神様が神武天皇に対し、神の使いである八咫烏を遣わします。 神武天皇は八咫烏の道案内のおかげで、紀伊半島の山岳地帯を乗り越えることができ、奈良の橿原までたどり着くことができたのです。 そして橿原で体制を立て直し、もう一度敗れた地の民とリベンジマッチをし、見事勝利をつかむことができたのです。  【写真:大台ケ原にある神武天皇の像】 紀伊半島を越える道案内役として、そして奈良を治めるために大きく貢献したことから、八咫烏は「導きの神」「旅の安全をつかさどる神」そして「勝利の神様」として祀られることとなりました。 というわけで奈良における伝統的な神様として古くから祀られてきました。だから、奈良を拠点とするサイクルショップシルクロードのシンボルマークになりました。また導きの神様、旅の安全の神様はサイクリストにとってぴったりの神様なのです。  【写真:宇陀(榛原)にある八咫烏神社】 余談ですが、神武天皇がナガスネヒコという人と戦って勝利を収めた場所はお店から自転車で5分ほどのところと言われています。 八咫烏は和歌山と奈良に伝わる導きの神であり、交通安全の神であり、勝利の神様なのです。 サッカー協会のシンボルになっていることが有名ですよね。また、吉野の地酒の名前であったり、あと自衛隊の部隊のシンボルになったこともあるそうです。 上記内容は僕の知っている知識で語っているだけなので、間違いもあるかもしれませんが、その時はこっそり教えてください。しれっと内容を書き換えます。あ、上記画像の神武天皇の移動したルートは僕が勝手に想像で作ったルートです。事実はしりません。 |
|||