  since2022 |
サイクルショップシルクロード 奈良県生駒市真弓2丁目4-10 ℡0743-79-9592 (定休) 水曜日 |
||
 |
 |
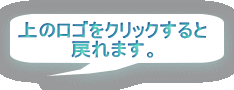  |
||
| ここはヤタガラスのフレームづくりについてちょっとばかし語ります。ベテランとは到底いえないですが、店長はこんなことを考えながら作ってるんだなあ、と思ってもらえるくらいでいいです。何いっとんねん、と思うかもしれませんが、あくまで僕の持論です。いや、店長!それ間違っていますよ!それは違うんじゃないか!と思った方はどんどん指摘してください。それもいいフレームを作るためのいい材料になります。 |
|||
| ヤタガラスのフレームづくりは基本的にはTig溶接で作られます。なぜクロモリフレームで主流のラグでの製作しないのかというと、いや、別にラグでの製作をしないわけではないんです。まずはTig溶接での製作をします、ということです。 ではなぜTig溶接なのでしょうか。 あ、その前にTigとかラグとか一体なんぞや?という方にまず説明します。 |
||
==ラグフレームとは== |
||
| まずクロモリフレームの多くに採用されているラグフレームはパイプとパイプを引っ付けるのにラグという一回り太パイプを使用します。太いパイプにフレームパイプを差し込んでそこにロウという金属を溶かして流し込みます。ロウは接着剤の役割でラグとパイプを固定します。 昔から作られてきた伝統的な制作方法で、歴史があります。また、造形が美しく、所有する喜びがあります。クラシカルな雰囲気の自転車を好むのであればラグフレームいいのではないでしょうか。 しかし、ラグはフレームの接合に一回り大きなパイプを使用することにより、重量が重くなってしまいます。また、パイプ同士の角度、溶接位置を細かく変更することができず、設計が制限されてしまいます。 溶接位置では0.5mm、溶接角度で0.5度単位で突き詰める設計にはラグは向きません。※ラグから作成するビルダーさんならば可能だと思いますが、手間が半端なく大変です。 |
||
==Tig溶接とは== |
||
| Tig溶接は、電気の熱でフレームパイプを溶かし、つなぎ合わせる方法です。この方法だとパイプの接合個所、角度、位置を自由に設定でき、フレームの設計の幅が広がります。ラグのように接合に別の部品を使わないので重量が軽くなります。 では、デメリットはなんでしょう。まずは昔ながらのラグの美しさがない、ということです。好みですが。接合が難しく薄肉(0.5mm程度)のパイプの溶接は穴が開きやすく難しいです。あとはうまく溶接しないと溶接個所が凸凹し、見た目が汚くなります。 |
||
| とまあ、ラグフレームとTig溶接の僕の個人的に感じている違いです。 |
||
| で、何の話でしたっけ・・・あ、そうそう、というわけでよりよく走り、乗って楽しい、もっともっと走りたくなる自転車を作っていくには、溶接する位置や角度をミリ単位、0.5度単位で突き詰めていく必要があると考えていますので、現段階でヤタガラスはTig溶接を採用していきます。 将来的にはラグフレームも作ろうと思っていますが、現時点ではTig溶接にてフレーム制作を行っております。 ボトルゲージのネジやワイヤー受け、フォーククラウンはロウ付けで取り付けています。 |
||
| フレームづくりについてのこだわりをいろいろ語ってしまうとめっちゃ長くなってしまうんです。まあ、こだわりというか、ヤタガラス的自転車論みたいな感じですね。僕は物理に詳しくないので理論的に論ずるには知識不足なのですが、お店をしていろんなモデルの自転車を乗ってみたりジオメトリーを調べてみたりと、僕の中での理想の自転車ってこうなんじゃないか、って思って作っています。 | ||
| でも、やっぱり作ってみないと分からないこともいっぱいあって、結局トライ&エラーでバイクを進化させていく感じですね。それから・・・おっとっと、また長くなってしまう。 またどこか別の場所で語らせてもらおうかな。 とにかくヤタガラスは楽しい自転車を作るために、剛性やジオメトリー、乗り味などを細かく設計して作るために、現時点ではTig溶接で作成しています。 |
||